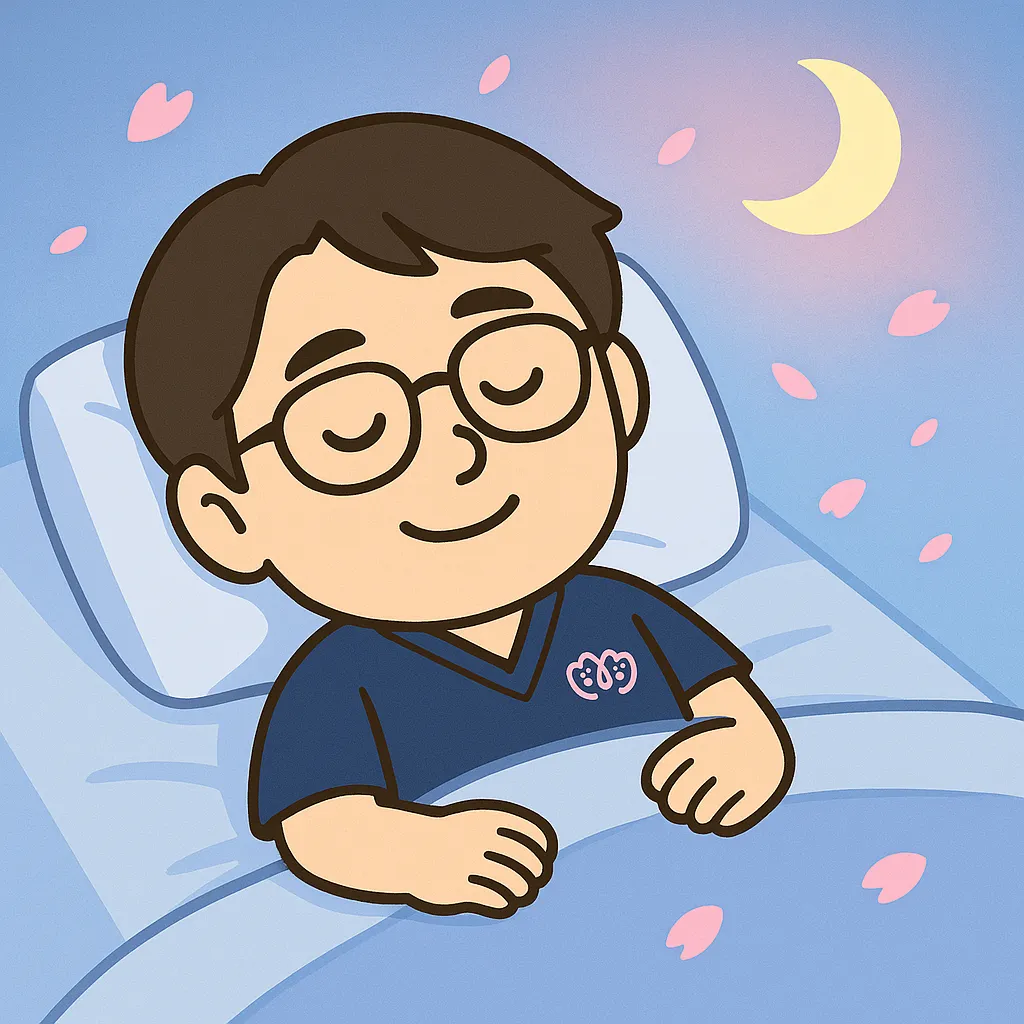
糖尿病の治療といえば食事と運動が基本ですが、実は睡眠も血糖コントロールに関わります。睡眠不足や質の悪い睡眠が続くと、血糖値が乱れやすくなるため注意が必要です。
眠っている間に、体を回復させるさまざまなホルモンが分泌されます。たとえば、成長ホルモンやコルチゾールはインスリンの働きを調整します。また、レプチンやグレリンといったホルモンは食欲のコントロールに関わっていて、レプチンは「食欲を抑える」、グレリンは「食欲を増す」ホルモンです。睡眠不足が続くとこれらのバランスが崩れ、血糖値が上がりやすくなったり、食欲が強まって食べすぎにつながったりします。睡眠時間を確保できていても、質が悪いとホルモンバランスに影響を及ぼすため注意が必要です。
さらに、睡眠の質を悪くする病気の一つに「睡眠時無呼吸症候群」があります。眠っている間に呼吸が止まることで、日中の強い眠気や疲れにつながるだけでなく、血糖コントロールを乱しやすくなることが知られています。糖尿病と睡眠時無呼吸症候群を併せ持つ方も少なくありません。適切に治療することで睡眠の質が改善し、血糖値の安定にもつながります。
眠りの質を改善するためには、日常の中でのちょっとした工夫も効果的です。たとえば、寝る直前にはスマホやパソコンを閉じること。ブルーライトの影響で脳が興奮し、寝つきが悪くなるためです。また、寝る時間や起きる時間をできるだけ一定にすることも大切です。さらに、寝る前はカフェインを避け、ぬるめのお風呂でリラックスするのもおすすめします。
糖尿病の治療は「食事と運動」だけではありません。質の良い睡眠をとることも、血糖値を安定させる大切な要素です。ぐっすり眠れることで心身が休まり、翌日にも良い影響を与えてくれます。
睡眠について考えることは、糖尿病の治療と前向きに向き合うための大事な一歩です。食事や運動と同じように、日々の睡眠にも目を向けてみませんか?主治医と相談しながら、自分に合った生活リズムを見つけていきましょう。